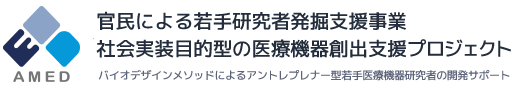2021年7月2日、東京大学にて令和2年度・令和3年度採択者によるラウンドテーブルディスカッションが開催されました。このイベントでは、ゲストスピーカーに国立研究開発法人 国立循環器病研究センターの朔啓太氏、および本事業PS(プログラムスーパーバイザー)高山修一氏を招いて講演・講話を実施。その後、令和2年度・令和3年度採択者がディスカッションで意見交換を図り、お互いの交流を深めました。
知識・経験ゼロからのクラスIV医療機器開発
スピーカー
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター
循環動態制御部 制御治療機器研究室長
朔 啓太

医療機器開発にいたる経緯
私は本事業の前進となる先端計測事業のサポートを受け、知識や経験がゼロからの状態で医療機器開発をスタートしました。ここでは、その経験を報告します。
心不全は、一度発症してしまうと増悪寛解を繰り返し、不良な転機をたどります。近年では「心不全パンデミック」も危惧されており、医療費の上昇や医療リソースの圧迫などが社会問題化しています。
私は自律神経による循環調節が専門で、九州大学で循環器内科研究員だった当時は電気的に自律神経活動へ直接介入して循環器疾患を治療する機器開発が増加しておりましたので、こうした研究によってどうにか心不全の増悪を抑えることができないかと考えました。
自律神経は、体を調節する恒常性維持のカギとなります。例えば、急に立ち上がったときでも頭の血圧は一定に保たれることで気絶を回避できるようにできています。つまり自律神経の高速な調節が働くことで、私たちは日常生活を送ることができるわけです。ところが、心不全になるとこの自律神経の調節が大幅に崩れてしまいます。そこで、自律神経のさまざまな場所に介入する治療が開発されています。
そのなかでも私は、迷走神経に着目しました。迷走神経は脈の調節をつかさどるだけではなく、代謝やホルモン、交感神経など多面的に作用して、心臓を保護する作用を持つことが1980年代の研究より明らかになってきました。しかし迷走神経刺激は、強度を上げれば痛みや反射も強くなるため、疾患毎に刺激強度や効果機序、刺激時間を考慮することが必要です。こうしたことから、急性的電気刺激と慢性的電気刺激の両面からデバイス開発に取り組みました。
AMED採択で始まった医療機器開発
私は2つの事業でAMEDの支援をいただきました。1つは、上大静脈にカテーテルを留置して迷走神経を刺激する技術である「心筋梗塞治療用迷走神経刺激カテーテル」。もう1つは、「血圧を操る新型動脈圧反射刺激装置」という、動脈圧反射機能を再建する血圧調節デバイスです。
まず心筋梗塞治療用迷走神経刺激カテーテルの開発についてお話します。迷走神経は、上大静脈と気管に挟まれる形でほぼ直線的に走行しており、カテーテルでの刺激が可能です。私は2017年に、心筋梗塞の急性期に2時間ほど刺激することで、徐拍効果や梗塞サイズ縮小効果だけでなく、心不全進行抑制効果が得られることを示した論文発表にたずさわり、この技術を使ってデバイス開発をしたいと考えました。そのためには、迷走神経を効率的に刺激できる多電極配置のカテーテルデバイスと、刺激アルゴリズムを用いた専用刺激装置という2つの技術開発が必要です。
しかし当時の私は、一体「誰が作り社会に普及させるのか」という視点がまったく抜けた状態でした。それはデバイス開発の流れを俯瞰的に見ることができていなかったからです。動物を用いた基礎的な研究、企業との共同研究や開発物の検証、治験。どれにおいてもスポット的なかかわりとなり、開発全体の流れを把握できていないということが医学部研究者には起こりがちです。私の場合はとくに、「研究から開発にどう移すのか」をまったく知らない状態でスタートしました。
開発を実現するには、やはりパートナーが必要です。私の場合は、協力を得た医療機器ベンチャーとつながりのあるアメリカの機器製作会社を利用して、どうにか自分が思う形状の試作品製作を実現できました。
このデバイス開発の進捗状況は、先端計測プロジェクトから医工連携事業になり、これから臨床試験を行う段階で、PMDAに治験の相談などを行っているフェーズです。前途多難ですが、さまざまなサポートをいただいて、どうにか前に進んだ事業です。

一方で、医療機器開発の現実をより深く学んだのは「血圧を操る新型動脈圧反射刺激装置」の開発のときでした。動脈圧反射は交感神経を介して血圧を負帰還制御します。これを利用したBAT(baroreflex activation therapy,頚動脈圧受容器反射刺激装置)が10年ほど前に登場しました。
BATの問題点は、動脈圧反射の本来の機能が血圧変動を抑えることであるにも関わらず、BATでは一定の電気刺激であるため変動は抑制できないということです。そこで私は、血圧をフィードバックするアルゴリズムを搭載し、刺激で血圧変動まで抑制できるデバイスとして「血圧を操る新型動脈圧反射刺激装置」の開発に取り組みました。
これは理論としては非常に夢のある技術ですから、論文化するまでは容易に進みました。しかし、実際にこのデバイスをヒトに使うとなると、非常に難しい点がみえてきました。例えば、植込み型デバイスを日本でどう開発するのか、変動を抑制して予後が良くなったエビデンスはあるのかなど、根本的な疑問を突きつけられるわけです。
結果として、このプロジェクトはAMED事業としてStep upすることができませんでした。
知識・経験ゼロから始めて感じたこと
この事例から学んだのは「実現=臨床実験できるハード」だということです。動物実験は最初の一歩でしかなく、アイデアだけがよくても評価されません。大切なのは実験器具を超えて、ハードをどう作るかで、それができなければ社会実装まで到達できないのです。それを踏まえ、開発しようとするデバイスが「本当に患者に必要か?」という視点は非常に重要です。いくら先進的な技術があるからといって、患者の利益にならないものを作っても無駄になってしまう。それを実感した事例でした。
若手育成を目的とした本事業の意味は、おそらくコンセプトを絞り込んで見た目の短期ゴールを達成することではありません。コンセプトの変更や練り直し、ときには勇気ある撤退も選択可能だということが、本事業の本当の意味ではないかと思います。
私は、自身の医療機器開発の経験を通じて、以下のように感じました。まず、一般に医学部で医療機器開発を知ることのできる機会は少なく、自身で行動して「know who(誰が何を知っているのか)」を得ることが大事だと感じました。多くの人の助けを借りてどうにか前身することができ、治験実施が見えたプロジェクトも生まれたのです。一方、そのままのコンセプトでは開発を進めても実用化までのロードマップを描けないことを認識させられたプロジェクトもありました。
医療機器開発に携わる研究者としての在り方とは
企業導出という課題をシステム的に乗り越えることは難しく、結局近道になるのは、自身の研究文脈の構築とそれに伴う人脈形成だと感じました。また、基礎研究からシーズを創出するだけが医療機器開発ではなく、それぞれのパートにアカデミアが介入すべきサイエンスが存在します。
研究者のデバイスへの関わり方はさまざまですが、スポットでは全体を理解することは難しく、やはり一連の流れを経験することは非常に重要です。本事業を通じて、医療機器開発の一連のプロセスを経験される先生方が増え、そして同じ志を持つ仲間が増えれば嬉しく思います。
PS講話・ブレイクアップディスカッション

続いて、本事業プログラムスーパーバイザーの公益財団法人医療機器センター 上級研究員 高山修一氏による講話がありました。
講話では、ご自身がオリンパス株式会社で取り組んでこられた数々の事業の成功例や失敗例に触れ、事業開発のプロセスとポイント、マーケットシェアの重要性などについて説明がありました。また、ビジネスは現場を知ることが最も大切で、先見性をもって計画的に進めるべきだというお話がありました。
その後、令和2年度および令和3年度採択者を交えたブレイクアップディスカッションが開かれました。ディスカッションは会場参加者とオンライン参加者が計4チームに分かれてハイブリッド形式で進行。「医療機器開発でどのような課題を感じているか」をテーマに意見が交わされ、各チームから以下のような内容が共有されました。
・ニーズとシーズそれぞれが、いわゆる“死の川”を渡りきれていない。基礎研究から開発研究への移行にハードルを感じる。ニーズを持つ臨床医がシーズに巡り会えないのも問題だ。マッチングイベントなどで人脈を広げることで解消できればいい。
・AMEDに採択された事業であることをレバレッジして事業化のプロセスを加速したい。一方で、企業の決裁スピードが追いついていない課題感がある。
・本事業で研究と医療機器開発の違いを知ることができた。サバティカル制度などで企業や大学病院に滞在し、じっくりと現場を知ることができたらいい。
・パートナー企業を探すにあたっては、学会などを利用して積極的に自分自身の研究をアピールする機会を増やすことが一つの方法だ。パートナー企業を選ぶ際には、企業の能力をしっかり見極めるべきで、それにはきちんと製造販売ができるかどうかがポイントになる。
・知財戦略では、競合となる特許との関係を理解して、周辺特許をしっかり押さえていくことが重要だ。
・シーズとニーズがうまくマッチしていることを確かめるために、開発に関わる人との間で横展開を強める必要がある。オンラインサロンなどショートトークで困りごとを共有できるイベントがあるといい。

こうした企業との向き合い方、ニーズや人脈の重要性などの意見共有に対して、最後に高山氏より「企業はWin-Winの関係を求めている。技術がビジネスにどうつながっていくかを明確に示すには、技術の革新性が重要なポイントだ。研究者側も企業の戦略を理解しておくとよい。最初は市場が小さくてもトップのシェアを獲れば問題ない」というアドバイスがありました。
また朔氏からは「今のシーズがどのフェーズにあるのかを考えて、自分のやりたい研究の方向性をしっかり見つめることが重要だ。企業から自分の認知を得るためには、オンラインサロンなどで人脈を広げるのもいいが、専門分野の研究会を立ち上げて会員を増やすなど、インターネットを利用した自己ブランディングも有効だ」とコメントがありました。
本イベントは、令和2年度と令和3年度の採択者がお互いに具体的な課題感を共有し、開発プロセスについての不明点などに助言を得るなど、双方向でコミュニケーションを図る貴重な機会となりました。